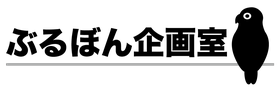甘柿と渋柿、実家の畑には二本の柿の木が並んでいる。夏の終わりに畑仕事をしていると、たくさんの青い実が付いているのが見えた。今年は豊作にちがいない、と秋の到来を待ちわびた。
スーパーに出回り始めた柿は、軒並み高かった。前年の五割増しくらいの値が付けられている。産直市でも手頃なものが見つからない。実家でもらってくるのが賢明だと思った。
十月に入った最初の日曜日、玉ねぎ植え付けの準備のために、母と畑を訪れた。畑を耕した後、休憩中に柿の木を見上げると、橙色に熟れた実が枝に付いていた。よく見ると大半は渋柿の実で、甘柿は少ない。しかも食べ頃に見える甘柿は既にヒヨドリのごちそうになっていた。わが家では長い間、渋柿は眼中になかったのだが、あまりにも無念だったので、取って干し柿にしてもらおうと思った。しかし渋柿も、ほとんどの実が枝の高い所にあって、手を伸ばしても届かない。
「先を割った青竹を持ってこんと取れんよ」と母は言うが、家の竹林は畑から遠い。倉庫の高枝切り鋏を持ち出した。
柄が一間ほどの鋏を持って、腕を伸ばす。
「枝は少しぐらい折れてもいいよ」
母の言葉に、遠慮なく柿を落とす。青くないか、崩れていないか、一つ一つ品定めしながら、足元のバケツに放り込んだ。鋏が届く高さの柿は全て取ったが、もう少し欲しい。手が届く枝をつかんで引いた。下がってきた枝に、母が鋏をかける。畑づくりも忘れて、バケツ一杯になるまで柿もぎに夢中になった。
「一個だけ、葉っぱも残しといて」
絵手紙の題材にするのだと母が言った。
実家で昼食を済ませ、帰り支度を始めると、母が食べ物や野菜を袋に詰めてくれた。「今晩食べんさい」と容器に詰めた栗ご飯、昼に食べきれなかったおかずもある。勝手口を出ると、足下の大きな袋に柿が入っていた。紐も入れてある。後ろから声がした。
「自分でやりんさい」
後は母に任せて、出来上がったころに食べに帰ろうと思っていたが、その画策は見破られていたのだろうか。よくよく考えると、水分が抜けて固くなった干し柿を好んで食べるのは私だけだ。父も母も齢を重ね、歯が丈夫ではない。渋柿の木を長年放置していたのも、食べるのが億劫になったからだと気付く。
帰宅して、二十二個の柿の皮をむいた。思った以上に手間がかかる。新聞紙の上に橙色の小山ができた。蔕につながる丁字の枝に、紐を縛り付ける。母の言いつけ通り、熱湯にくぐらせて、物干しに掛けた。
柿を吊るして四日経った。姿は一回り小さくなり、表面に皺が見える。鮮やかな橙色は、くすみがかってきた。干し柿が食べ頃を迎えたとき、母の絵手紙が届きはしないかと、ちょっぴり期待している。
中国新聞文化センターの講座「いい文章を書く 文の力で心をみがく」に提出した随筆です(2020年10月執筆)