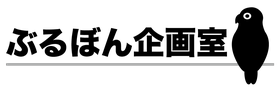小学生の頃、シールのおまけがついたチョコ菓子「はりはり仮面」が流行った。親から駄賃をもらえば、駄菓子屋に直行して、はりはり仮面を買い、友だちとシールを見せ合っていた。ブームは過熱して、毎日のように誰かが新しいシールを見せてくれた。だが、定額の小遣いを持たない一年生の子供が、四十円もする菓子をそ¬うそう頻繁に買えるわけがない。シールが欲しい。だがお金がない。その悩みを解決する手段があった。
「たけはる、儲けをしようや」
同級生の二人がしたり顔で誘ってきた。彼らの手の中には、はりはり仮面があった。儲けたお金で買ったのだろう。うらやましい。
「すごい。僕もやりたい」
「ほいじゃあ、明日は一緒に行こうで」
いったいどんな儲けをしたら、はりはり仮面が買えるのか。次の日が待ち遠しかった。
二人と合流して向かった先は、近所のくみあいマーケットだった。店に入り、お菓子売り場を物色する。
「おい、これじゃ」
「たけはる、お前もやってみい」
二人に促されるままに、着ていたシャツの中にはりはり仮面を入れた。ズボンのゴムの上で止まっているせいで、お腹が膨らんでいるようにも見える。平然と出口に進む二人の陰になるように、小さくなって歩いた。
「欲しいものがなかったけえ、帰ります」
レジのおばさんに挨拶して店を出た。
「今日も上手いこといったで」
「わしらは天才じゃのう」
二人は袋を開けてシールを見せ合う。僕は胸の鼓動が鳴りやまない。はりはり仮面を手に入れた喜びよりも不安のほうが大きかったが、「もうしない」とは言えなかった。
次の日もくみあいマーケットで儲けをすることになった。
「今日はお前が言え」
レジを通る時の大役を、二人は僕に振る。昨日見たのと同じようにすればいい。ランニングのお腹のあたりにはりはり仮面を忍ばせて、三人でレジの前に立った。
「欲しいものがなかったけえ……」
「あら、それは何かいね」
言いかけた途端に、おばさんが僕のお腹を指差した。言い訳のしようがない。三人とも隠し持っていたはりはり仮面を差し出して、家に帰してもらった。きつく叱られたり、親を呼ばれたりはしなかった。
数日経って、母に呼ばれた。レジのおばさんが、僕たちのことを母に伝えたのだ。母は僕を叱っている間ずっと泣いていた。流れ落ちる涙を拭きもしない。母をそんなにも悲しませてしまったことがつらくて、僕も泣いた。もう母を泣かせるようなことをしたくないと、子供心に思った。
僕の初めての罪は、菓子泥棒だった。
中国新聞文化センターの講座「いい文章を書く 文の力で心をみがく」に提出した随筆です(2022年4月執筆)