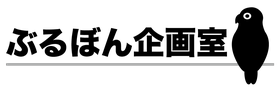(この投稿は堀行丈治のnoteからの転載です)
父の相棒
台風の進路が予報円から逸れ、週末の天気予報は「晴れ」になった。
―明日、畑仕事を手伝いに帰ります―
母にメッセージを送ると、私の帰省を喜ぶ返事の後に、一枚の写真が送られてきた。カーペットの上に、白い毛の塊がいる。猫ではないのかと尋ねると、数分が過ぎた頃に再び携帯が鳴った。
―猫だヨ 畑の近くの中川さんのところから貰ってきました―
父がかわいがっていた白猫が命を落としてから二年が経つ。気力を失ったような父を見かねた私は、何度か猫をもらい受ける話を持ちかけていた。しかし母はその度に、頑なに拒んだ。
「お父さんは欲しがっとるけどね。私はもういいと思っとるんよ」
先代の猫のように事故に遭って死んだらかわいそうだし、自分たちの年齢を考えると、最後まで飼えるか不安だと言った。私が同居していれば不安の半分は解消するかもしれないが、そうはいかないことは互いに分かっている。だが、年を追うごとに心身とも衰えてきた父を見ていると、別の不安が湧いてくる。
翌朝実家に帰ると、父の声が家の外まで聞こえた。
「腹が減っとるんじゃないんか。何かやっちゃってくれ」
勝手口から家に入ると、座敷に座って新聞を読んでいる父が、にこやかな顔をしている。視線の先では、昨日母が送ってくれた画像そのままの白い生き物が、何かを探しているかのように歩き回っていた。近づいてみて驚いた。子猫はあまりにも小さい。片手に乗るほどの大きさしかないのだ。昨日まで母猫と一緒にいたのだという。
「お母さんを探しようるんじゃろうのう。ほれ、こっちに来い」
父は子猫のことを少し不憫に思っているようで、何かと世話を焼こうとしている。子猫は彷徨いながらも、目の前に人がいれば誰彼かまわず寄ってくるものだから、余計にかわいく思えるようだ。
朝食を終えて一息ついていると、子猫は父の膝の上にいた。居心地が良いようで、その場から動こうとしない。二年ぶりに、父の相棒ができた。願わくはこの子がずっと、父の余生に寄り添ってくれていたらと思った。
ふと、父に寄り添うのは自分の役目ではないかと気付いた。私はこれまで父のことをあまり大切にしていなかった。それどころか、心のどこかで疎んじていたと思う。分からず屋で飲んだくれでせっかちで……と、悪い面ばかり見ていた。
子猫と私のどちらが、父の本当の姿を見ているだろう。小さな相棒を見ていると、私も真っ白な心で、父の残りの人生と付き合っていけるような気がした。
中国新聞文化センターの講座「いい文章を書く 文の力で心をみがく」に提出した随筆です(2020年10月執筆)
※写真はもう少し大きくなってからのものです