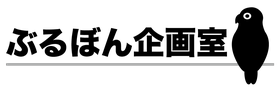この投稿は、堀行丈治のnoteからの転載です。
母の遺影
「私の遺影を撮ってくれんかね」
去年の暮れに、母が私に言った。生きているのに遺影とは……と、少々驚いたが、亡くなってから急いで葬儀屋に作らせるよりも、元気なときの姿を祭壇に飾ってあげたいと思った。「花がたくさん咲く季節に撮ろう」と約束して、この春を迎えた。
四月に二人で実家近くの寺を訪れると、その日は桜まつりが行われていた。いつもはほとんど人がいない場所なのに、大勢の家族連れや花見客でにぎわっていた。大きなレフ板を立てて撮っていると、恥ずかしがり屋の母は人目を気にしすぎて「もう帰ろうよ」と言い始めた。それでも半ば強引に、少しずつ場所を移動しながら撮り続けた。花見客のいない小高い丘まで来ると、母は落ち着きを取り戻した。心の余裕も出てきたのか、真白な八重桜が咲き誇るさまを、自分のカメラに収めていた。祭りの目玉行事である虚無僧たちの尺八の音が、麓から聞こえてきた。
湖のそばに場所を移し、ここでも桜並木の前に母を立たせた。私たちの他には、年配の夫婦と真っ黒なカワウがいるだけで、まつりの喧騒とは別世界だった。木漏れ日の中でシャッターを切った。何を話したのか、どんな言葉を掛けたのかも覚えていないが、内面からにじみ出るような、慈愛に満ちた優しい笑顔を撮ることができた。
子供の頃、母は私の写真をたくさん撮ってくれた。写真は今も四冊のアルバムに大切に保存されていて、一枚一枚に撮影日やその時の状況などが短文で記されている。被写体の私でさえ忘れている出来事でも、その説明を見ればおぼろげな記憶がよみがえる。アルバムを見た知人が、母の几帳面さに感嘆していたことを思い出す。
私は仕事柄、人物写真を撮ることが多いのだが、それまで両親の写真を撮ったことはなかった。初めて我が親にカメラを向けた春。母のありのままの姿を、一番いい顔で残してあげようと思った。
遺影写真は、湖畔の桜を背景に、母が微笑んでいる。白髪を染めるでもない、化粧もいつもと変わらない母の顔。「どうせ撮るなら、美容院ぐらい行ってくればよかったのに」と残念がる私に、母が言った。
「おじいさんとおばあさんのキリッとした遺影を見ると、今でも叱られているような気がして、目を合わせられないのよ。普通の写真がいいよ」
子供心に薄々感じていたが、母は祖父母に、私たちには見えないところで相当厳しいことを言われていたようだ。その厳しさは、祖父母の遺影の鋭い眼光にしっかりと現れていた。
写真は遺影サイズにプリントして、母の手に渡した。穏やかな笑顔の、私の大好きな母がそこにいる。
中国新聞文化センターの講座「いい文章を書く 文の力で心をみがく」に提出した随筆です。(2019年7月執筆)