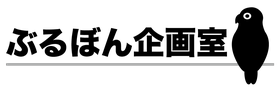報道によると今年の林忠彦賞は、視覚障害者が見える世界をイメージした写真集「ALT」だった。
作品を見ていないのに批評をしてはいけないと思うが、
写真表現、芸術としての意味があるのだろうかと疑問を持った。
障害者と世界を共有することは大切なことだし、視覚障害者の視界を疑似体験することにも意味はある。
だけどそれは、写真芸術とは異なるベクトルのものではないだろうか。
(芸術性よりも企画性が先行していないか?)
社会性と、創造性は等価なのか。
小説「ハンチバック」が芥川賞になったときと同じような感覚だ。
兆候は「むらさきのスカートの女」あたりから薄々感じていた。
誰も書いてない世界、誰も撮ってない世界を表現するために、飛び道具を使う。
「ハンチバック」の作者は当事者ではあるけれども、
作品が切り開いたフィールドが後の文芸にどれだけ影響を与えるのかと考えると
これ以上の発展性、拡張性がないように感じる。
いすれも、悪く言うと「一発屋」の作家になるのではないかと危惧する。
写真も文芸も、多くの作家が手を替え品を替え、さまざまな表現手法にトライしてきた。
今や何をどう撮っても、何をどう書いても、99%は誰かの模倣だろう。
そんな世界でオリジナリティを追求していると、行き着く先が飛び道具になるのは理解できる。
だが、飛び道具に瞬間的な面白さを感じることがあっても、リピートしたいと思わない。
創造性は普遍性とは対極にあるものだとは思うが、
新たな価値を生み出すものには、少しでも共感できる部分がほしいと思っている。