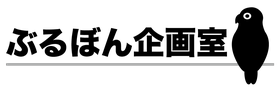西日を遮るカーテンの向こうで、駅前を往来する人の影が行き交う。黒檀の仏像たちが見守る中、古美術商の三浦敬太郎が茶碗を持ち上げて目を凝らす。赤茶けた肌に広がる細やかな貫入が浮き上がって見えた。
「どうだ。いくらぐらいの値が付くかな」
白石雅弘は身を乗り出して訪ねた。隣では息子の拓也が膝に手を置き、やりとりを見守っている。三浦は茶碗を覗き込んだり高台側に返したりと縦横に回しては、その都度手触りを確かめるように両手で包み込む。
「いい値がつくなら、お前の儲けが出るくらいで買ってくれたら……」
はやる気持ちを抑えきれず切り出す白石の言葉を遮るように、三浦が口を開いた。
「お前も古物商なら自分でも勉強しろよ」
「古物商といっても、リサイクルショップなのを知っているだろう。お前が俺に勧めたんじゃないか。リサイクルは儲かるって」
白石の店に拓也が訪ねてきたのは昨日のことだった。二十年前に別れた元妻との間に授かった息子と会うのは三年ぶりだ。手提げバッグから木箱を取り出し、白石の前に置いた。
「じいちゃんの遺品を整理していたら出てきたんだ。母さんが売りたいって」
「おじいちゃん、いろいろ集めていたんだな。でも俺の店は骨董屋じゃないから……」
「同業者に詳しい人がたくさんいるでしょ。養育費も満足に払わなかったんだからこれぐらいの奉仕はしろってさ、母さんが」
茶碗を調べてみると、赤楽と呼ばれるもののようだ。箱書きは読めないが、そっくりな筆字が描かれた箱の写真があった。
「これと良く似ていると思わない」
拓也が声を弾ませる。本物なら相当な時代物に違いない。古物商なんて海千山千の輩ばかりだが、唯一信頼できるのが高校時代からの友人、三浦だった。
三浦は茶碗を眺めては文献を読み、また茶碗の手触りを確かめる。この手順を何度か繰り返した後、白石親子に目をやった。
「箱は古い物だな」
「ということは、茶碗は古くないのか」
「そうだな。古い物に似せて作った現代物だ。だが作りは悪くないし、茶道具として使うにはいいんじゃないかな」
三浦は茶碗を布で丁寧に包み、箱に戻した。
「箱が八千円、茶碗は二千円でどうだ」
拓也は無念そうに手を組み、黙っている。
「売ったところで小遣い程度にしかならないし、犬の餌入れにでもしてやれ」
白石は箱を取り、拓也に放り投げた。拓也が箱を受け止めた時、怒号が響いた。
「何てことするんだ」
三浦の顔から血の気が引いていたが、白石と目が合うと、気まずそうに下を向いた。白石は笑みを湛えて三浦の肩に手を置いた。
「それで、本当はいくらするんだ」
(2023年 高橋一清講座「いい文章を書く 文の力で心を磨く」出品作品)